旅行の質が変わった。
物見遊山的団体旅行が影をひそめ、安・近・短の観光が主流となった結果、今まで観光資源とみなされなかったものが既存の観光資源にとって代わる現象が起きつつある。
これらは、ニューツーリズムや体験型観光、着地型観光と言われる旅行形態で、いわゆる観光地でない地域の魅力を体験するもの。担い手は、観光の主体だった行政や観光協会、旅館・観光施設だけでなく、商店街、地元農家、まちづくり系NPOや大学など、幅広い。そのため、地域づくりを通じた観光振興策として全国各地で行われている。
問われるのは、地域自らが地域の魅力を掘り起し、旅行商品に仕立て上げ、販売する「地域プロデュース力」。「ふじのくに観光躍進基本計画」ではこの「地域プロデュース力」を強化する方向に大きく舵を切っている。
県の伊藤秀治文化・観光部長は「旅行者の好みが変われば観光の中身も変わらなければならない。また、観光まちづくりを通じた地域のブランド化は避けて通れない。今回の計画はある意味、観光の“軸”を今の時代に合うように変えていくこと」と言い切る。
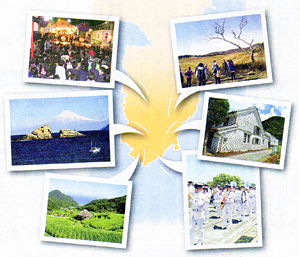 |
■伊豆各地のエリアDMOが地域の魅力を掘り起し、商品化し、情報発信する |
中でも力を入れるのが、DMOと呼ばれる仕組みの構築だ。 DMOとは、「Destination Management(Marketing) Organization」の略。観光プラットフォームとも呼ばれるもので、体験メニューのワンストップサービスから、観光地のマーケティング、プロモーション、集客、観光戦略の立案や事業計画のマネジメントまで幅広く行う。4エリア180コンテンツを提供する「阿蘇振興デザインセンター」(熊本県)や、小値賀島の暮らしそのものを民泊という形で商品化する「おじかアイランドツーリズム協会」(長崎県)などがその代表だ。 |