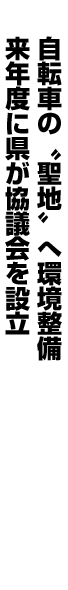 |
 |
■自転車関連施策を県が一元化 |
|
 |
| 五輪自転車競技(トラックレースとマウンテンバイク)の開催が決まった伊豆ベロドローム |
伊豆市の日本サイクルスポーツセンター(CSC)の東京五輪自転車競技開催発表後、同センターによると、各方面からの問い合わせや視察が相次いでいるという。こうした動きを見据えて同市は地元食材を使った「視察弁当」を開発中だ。今後、アクセス道路の拡幅や選手村の整備、競技施設の改修など、五輪開催に向けた準備が加速していく。
県内では、エコパスタジアム(袋井市)や富士スピードウェイ(小山町)を利用した自転車イベントが数多く開かれている。CSCも年間80を超える大会が開かれているが、ほとんどは関係者のみの参加にとどまっている。また、一口に「自転車」といっても、トラック・レース、ロードレース、アップダウンの多いオフロードコースを走るMTB(マウンテンバイク)やBMX(バイシクルモトクロス)などの競技に加え、景観を楽しむ観光サイクリングまで幅広い。
県は自転車への関心の高まりを戦略的に進め、地域振興に生かそうと、次年度から協議会を立ち上げる。観光、スポーツ、道路など自転車に関連する部局を横断的にまとめ、専門家、サイクリスト、地元自治体、警察などと「自転車を楽しむ」「自転車競技を応援する、支える」「基盤整備」の三つの視点で、「自転車の聖地・静岡県」を目指す。
 |
| 景観生かしサイクルネット整備 |
昨年秋に、県は自転車が盛んなイタリア・フリウリ・ヴェネチア・ジュリア州とスポーツ交流協定を結び、サイクリング大会への相互参加を通じた交流を始めた。県文化・観光部の山本東スポーツ交流課長は、「2020年までに国内外から訪れるサイクリストが快適に楽しめる環境を県内にも整備したい」という。具体的には、本県の魅力を生かしたサイクリングコースの選定や大会の開催、地元自治体の自転車施策への理解促進、選手をはじめ世界大会などを運営するスタッフの育成―などが予定されている。 |
 |
 |
■地域に開かれた自転車拠点に |
|
一足先に自転車を地域振興に結び付けようと活動しているのが、「県東部地域スポーツ産業振興協議会」(会長・三島信用金庫稲田精治理事長)だ。昨年度、県経済産業部商工振興課が音頭をとり、東部の自治体、企業を募り立ち上げた。地域の実情を反映した「サイクルスポーツ」「合宿スポーツ」「クラブスポーツ」の三つの部会で構成され、サイクルスポーツ部会は、誰もが安全で快適に自転車を利用できる環境整備を目的に、東部・伊豆地域に自転車コースのネットワークづくりに取り組んでいる。
スポーツサイクル(車輪が大きく、ある程度スピードが出る自転車の総称)愛好者は全国で1200万~1300万人と言われる。主に首都圏に多く、40~50代以上の生活面で比較的余裕のある層だ。富士山、駿河湾、伊豆半島を有する県東部・伊豆地域は、自転車を楽しむには最適な地域。首都圏からも近く、食の魅力や宿泊施設など観光資源にも事欠かない。レンタル自転車回収の仕組みやゲストハウス、民泊などを組み合わせれば外国人観光客を取り込める可能性もある。
手本となるのは瀬戸内しまなみ海道だ。年間約20万人のサイクリストが訪れ、外国人観光客も増加傾向にある。こうした動きを受け、日本政策投資銀行と瀬戸内海を囲む中国・四国地方の7地方銀行が新会社を設立。総額100億円規模の観光産業活性化に向けた投資ファンドを今春立ち上げる。同部会でリーダーを務めるシードの木部一社長室次長は「サイクルネットの整備は、既存の観光振興ができなかった地域連携や面での展開を図り、地域に新しい投資を呼び込む手段となる」とその意義を強調した。
 |
| サイクルスポーツ部会が進める「県東部・伊豆地域サイクルネット」のイメージ |
今後、同部会では、県に働きかけ、県で設置する協議会内で、各種計画の収集や調査、自転車の走行環境整備、法定外サインや標識を検討し、連携を図って対象地域の自転車環境整備を呼び掛けていく予定だ。
|
 |
 |
■地域に開かれた自転車拠点に |
|
 |
| CSCで毎年開催される「ツアーオブジャパン」には、自転車競技愛好家が詰めかける |
東京五輪自転車競技会場のCSCは、世界自転車競技連合から、選手やコーチ・スタッフの育成強化部門のアジアの拠点に指定されている。2002年からアジア各国より広く選手、スタッフを受け入れ、特にジュニアやユースの育成に定評がある。CSCで研修した若者が五輪や世界大会、ワールドカップなどでメダルを取る回数も増えてきた。トラック4カ所、ロード、MTB、BMXの各コースと宿泊施設を備えているため、設備面でもアジアの自転車競技の拠点となっている。また、日本のオリンピック、パラリンピックのナショナルトレーニングセンター指定も受けている。
大会や合宿も度々行われている。14年度は82大会、1万420人が訪れた。合宿は266団体、延べ3703人、ナショナルチームのトレーニング日数は延べ351日を数える。
世界レベルの施設だが、地元でもこうした内容はあまり知られていない。「五輪開催決定で、視察や問い合わせが増えた。これを機に、地元の皆さんにも広く親しまれるような活動を活発化させたい」とCSCの野田尚宏競技振興部課長。
すでに、地元小学生向けに五輪の自転車競技を体験する教室を開いたり、伊豆総合高校の体育の授業に自転車競技を取り入れたりしている。また、三島市の男子バレーボールチーム「東レアローズ」がトレーニングの一環で同施設を利用するなど、今までとは違った“外部”との交流を行っている。
CSCは自転車競技の振興だけでなく、自転車の生涯スポーツ化も推進している。野田課長は「自転車を楽しみながら健康寿命を延ばす、そうした文化が根付けば、それも一つの五輪レガシー(※)だ」と語る。
今月26日から4日間、アジア自転車競技選手権大会のトラックレースが伊豆ベロドロームで開かれる。地元伊豆市、隣接する伊東市、伊豆の国市民と高校生以下は無料で観覧できる。こうしたことも自転車競技への理解を深める活動の一環だ。「プロの選手になると時速70キロを超す。そのスピード感と迫力を生で見て、感じてほしい」(野田課長)。
五輪は世界中から多くの自転車競技ファンが集まり、熱い声援が送られるであろう。県自転車競技連盟の松村正之理事長は「地元の人が競技のルールを学んだり、選手を覚えたりして、訪れた人たちと一緒に熱く応援することが、本当の意味でのおもてなしになる。地元と協力して、伊豆で五輪が開かれて良かった、と言われるような大会にしたい」と意気込む。
2020年まであと4年。その間に世界各国から訪れる自転車愛好家に支持される環境整備が間に合うか、五輪終了後、地域にどのようなレガシーが残るのか、関係者の努力を期待したい。
※五輪レガシー…五輪開催を通じて開催都市、開催国に長期にわたる、特にポジティブな影響。1964年の東京五輪では、東海道新幹線や首都高速道路の整備、体育の日の制定などがなされた。 |
 |
|